〜発達障害でも本番に強い〜
ADHDの“困った特性”は、実は大きな才能かもしれない。

「どうして集中できないんだろう」そんな思いを抱えて、夕暮れの中で立ち止まる。
「どうして集中できないんだろう」
「また忘れてしまった」
「自分だけ落ち着きがない気がする」
──そんなふうに、ADHD的傾向を“生きづらさ”として抱えてきた人は多いのではないでしょうか。
でも、もしその“困った特性”こそが、ある状況では才能として輝く可能性があるとしたら?
今回は、「ADHDは才能になりうるのか?」がテーマです。
これは、私自身の体験と『多動脳』の内容をもとに書いています。
飲食・音楽・空手の3つの実例から、「自分のスイッチが入る場所」を一緒に探していきます。
※この記事を読む前に、こちらの記事から読んでいただくと、より理解が深まります。
👉 【ADHDシリーズ第1弾】“生きづらい脳”の正体──落ち着きがない・集中できないのは狩猟民族の名残?
👉 【ADHDシリーズ第2弾】ADHDが生きづらさに悩むあなたへ──“得意”を活かす生き方ガイド【環境・仕事・心の整え方】
🌀なぜADHDの特性が本番に強いのか?
※このサイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
ADHD(注意欠如・多動症)は医学的には発達障害の一種として扱われていますが、その本質は「脳の働き方の個性」とも言えるものです。
たとえば、ADHDに見られる代表的な特性にはこんなものがあります。
• 気が散りやすく注意力が続きにくい(刺激への感度が高い)
• 衝動性があり落ち着きにくい(判断と行動が速い)
• 動き続けてしまう傾向がある(常に行動し続けるエネルギー)
これらは、学校や職場などの「静的な環境」ではマイナスとされがちです。
ここで言う静的な環境とは、じっと座り、同じ作業を長時間続けることが求められる場所のことです。
授業で黙って話を聞き続ける場や、単調なデスクワーク中心の職場では、「動かない」「反応しない」ことが良しとされがちです。
しかし、環境が変わればどうでしょう?
刺激が多く、即応性が求められる場面では、むしろ突出した才能として作用するのです。
そして、これこそが『多動脳』が提唱する「ADHDは欠点ではなく可能性だ」という核心です。
⸻
🚀発達障害でも才能として開花した実例たち
🍽 飲食店オーナーの例

瞬時の判断と行動が求められる環境では、人は自然と力を発揮しやすくなる。
『多動脳』の中で紹介されていたある料理人は、学生時代は問題児扱いされ、落ちこぼれとして見られていたといいます。
しかし飲食の現場に入り、厨房でのピークタイムにこそ自分の能力が最大限に発揮されることに気づきます。
「複数の注文が飛び交う混乱の中で、自分の頭は逆に冴えわたり、必要な判断が即座にできる」と語る彼は、今では人気飲食店のオーナーに。
刺激への感受性と瞬時の判断力、多動的な行動力──すべてが料理人としての武器となっていたのです。
🎵 トップミュージシャンの例

観客の視線や緊張感がある「本番の場」でこそ、集中力が一気に高まる人もいる。
また、同書で取り上げられていたミュージシャンは、日常生活では忘れ物や時間管理が苦手だったと言います。‹
しかし、音楽の世界に入った途端、彼は“降ってくるような曲のひらめき”に導かれ、数々のヒット曲を生み出してきました。
音に没入し、昼夜を忘れて作曲する彼の集中力は、「過集中」というADHDの特性の一つ。
通常では持続できないような深さで物事に入り込める力が、クリエイティブの場では圧倒的な才能として機能していたのです。
🥋 私・Kenji@LifeSpiritの空手体験

少し変わって見えても、その場に合えば力を発揮できる。
少し意外な画像かもしれませんが、私自身もまた、ADHD的傾向を持つ者として、空手を通じて“スイッチが入る感覚”を何度も経験してきました。
入門当初、稽古は苦しいものでしたが、上段回し蹴りを顔に受けて倒れたり、みぞおちに一発もらって膝をついたり、先輩たちに圧倒されるばかり。
でも、試合になると世界が一変するのです。
観客の声も、道場の空気も、一切が遠のいて、目の前の相手の動きだけがスローモーションのように見える。
体が自然に反応し、冷静な判断が瞬時に下せる。
普段の稽古では出なかった力が、なぜか試合になると出てしまう。
道場の先生や仲間たちからは、
「お前は本番に強い」
と言われてきましたが、今思えばそれは、「本番=強い刺激」という場面で、私の脳の“覚醒スイッチ”が入っていたのではないかと思うのです。
⚡刺激感覚に強く反応できる脳

3つの例に共通していたのは、「強い刺激を受けた時に脳が活性化し、普段以上のパフォーマンスを発揮できる」ということ。
これはまさに、多動脳の核心的特徴である「覚醒系の特異な働き」によるものです。
| 共通項目 | 飲食店オーナー | ミュージシャン | Kenji(空手) |
|---|---|---|---|
| 刺激による覚醒 | 混雑の厨房で集中力が高まる | 曲が降りてくる瞬間に没頭 | 試合での異常な集中 |
| 多動的対応力 | 複数の注文を処理 | 音の細部を聞き分ける | 相手の動きを瞬時に読む |
| 過集中 | 一点に集中し迅速に動く | 数時間ぶっ通しで作曲 | 技を出す判断が冴える |
💫仏教的視点:苦の中にこそ“光”がある
仏教では「苦集滅道」という四つの真理を説きますが、その中でも「苦」はスタート地点です。
避けるべきものではなく、乗り越えた先にある可能性に気づくための入口でもあります。
私の道場での稽古の苦しみも、飲食店オーナーが過ごした不遇の学生時代も、音楽に出会う前の彼の葛藤も、すべてが“才能を育てる土壌”だったのです。

遠回りに見える道にも、意味は宿っている。
🛡️まとめ/あなたの中の“困った”は、武器に変わる
ADHD的な傾向を「直さなければならないもの」と決めつけるのではなく、「環境が合っていないだけかもしれない」と見方を変えてみる。
そこから始まる可能性が、誰にでもあるはずです。
- ADHD的特性=才能になりうる
- 刺激や本番の中でこそ覚醒する脳の特性
- 多動性や衝動性は、“適材適所”で活きる能力
「スイッチが入る瞬間」を見逃さず、自分の才能と出会う勇気を持ってほしい──この記事を通して、そう伝えたいです。
最後に「あなたのスイッチが入る瞬間はいつですか?」コメント欄でお聞かせください。
⸻
このような記事もたくさん読まれていますので、お立ち寄りいただければ幸いです。
👉関連記事:変わった実感がないのは、実は“本物の変化”のサイン|仏教と空手から学ぶ自己成長
▼あわせて読みたい
ゴルフは心の修行──“脱力”と“無心”が導くもうひとつの世界
📚参考書籍紹介
ADHDを「治すべき欠点」ではなく、環境によって力を発揮する“脳の個性”として見直すきっかけを与えてくれる一冊です。
📘『多動脳 ADHDの真実』アンデシュ・ハンセン 著(新潮新書)
📌 合わせて読みたい:生活に関わる“大事なテーマ”はこちら
⇡ 記事の最初に戻る
🌿 最後まで読んでくださってありがとうございます。
心が少し軽くなったら、LifeSpiritトップページに戻って、ほかの記事もゆっくりどうぞ。
※記事中の飲食店オーナー・ミュージシャンの話は、上記書籍を参考に要約・再構成したものです。著作権に配慮し、出典を明記しています。




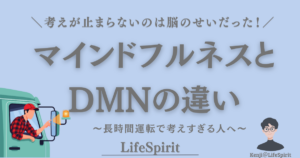







コメント